臨床検査技術科
尿の採り方について
泌尿器科、腎臓内科、小児科等では事前に尿スピッツと採尿コップをお渡しし、各ご家庭で採尿を、尿を持参していただく場合があります。
尿検査には、「中間尿」を用いた方が検査精度を高めることができます。
- 尿は、最初と終わりの部分を捨てて、中間部分(中間尿)を採尿コップに入れてください。
- 尿量は採尿コップの1/3ほどあれば充分です。
- 採尿後はお渡ししているスピッツに移し変えてください。

よくある質問
Q: どうして出始めの尿は採ってはいけないの?
A : 出始めの尿は、尿路系以外からの混入物(女性では膣や外陰部からの細胞や細菌・分泌物、男性では精液などに由来する精子や分泌物など)を多く含み検査結果に影響を及ぼすことがあるため、中間尿を採っていただいています
Q: 生理中の場合はどうすればいいの?
A: 生理中の尿でも検査はできますが、正しい判定ができない項目もあります。尿を医療スタッフに渡す際、お申し出ください。
Q: 少ししか尿が採れなかったのですが・・
A: 採れた分だけでもスピッツに入れご持参ください。必要量に足りる場合もありますが、足りない場合は来院後に再度取り直していただくことがあります。
便の採り方について(便潜血)
- 便の中に血液が混ざっていないかどうかの検査です。
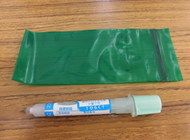
- 注意!
生理中の採便は避けてください。痔疾のある方は、その旨を主治医にお伝えください。 - 事前にお渡ししている採便キットを使用します。
① まずは大便をしましょう!!
便に水がつかないように、水に流せるペーパーなどを便器内にひきます。
水の中に出してしまうと、便器に付いていた他人の便と混ざってしまう可能性があります。
② 付属の棒で便の表面をまんべんなく擦り採ってください。

③ 採取したら元の容器に戻します。
しっかりキャップをし、よく振った後、緑色の袋に戻してください。
注意!
採便後、提出が翌日以降になる場合は冷蔵庫に保管してください。
喀痰の採り方について
喀痰の検査には、主に2種類あります。
細菌検査
感染症の有無や原因菌を突き止めます。
細胞診検査
がん細胞がないか調べます。
できるだけ早朝の起きた直後に採りましょう!
① うがいをして、口の中をリフレッシュします。
② 水を飲みましょう。痰がやわらかくなり、出やすくなります。
③ リラックスしましょう!
肩の上げ下ろしを数回行い、肩の筋肉をほぐします。
首を左右に曲げ、首の筋肉をほぐします。
上体を曲げたり反らしたり、胸の筋肉をほぐします。
④ 鼻から息を吸い、口から息を吐き出します。
何度か繰り返すことで、痰が出やすくなります。
⑤ 痰が出そうだ!となったら、大きく深呼吸をした後、強く咳をして痰を出します。
出来るだけ、鼻水や唾を混ぜないようにします。
|
痰ではなく唾液ばっかりだと 白血球があまり見られません |
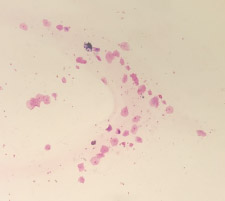 |
|
上手に採取できると・・・ 白血球が菌を食べているところがみられます |
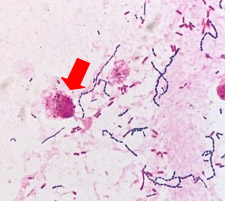 |